2012年08月12日
不惑まであと3年
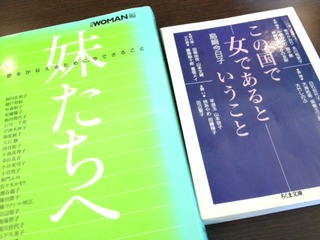
「不惑」って言葉は、すこぶる仕事の出来る知的女史のプロフィールをキッカケに知った
いわゆる”40歳”を表現する言葉。
ここ数ヶ月、三十路手前にも感じた何ともいえない焦燥感に駆られて、暇さえあれば本屋に通って自分を納得させる言葉を探していた。
別に現実が不幸って訳じゃない。
むしろ三十数年の人生で、なかなか幸せな状態で生活しているし自分が好きな事を仕事にしているし、多分凄く幸せといっても良い環境に居ると思う。
10代の数年間、心ない他人の暴力で人間不振になり「起きてたら死んでいたらいいのに。」と考えながら寝床についていた時代にタイムトリップして、いまの私を見せて励ましてやりたい位に人生を楽しんでいるような気さえする。
それなのに、なんだろうねー10年ごとにやってくるこの言いようの無い感情は。
20代後半の時の理由はハッキリしている。
当時結婚を考えていた相手と別れたことに始まり、色恋ばかりに走り仕事で特別なキャリアを積んで来なかった自分への情けなさや後悔に苛まれ、現状を打開するためには、何かを変えないといけないことに気づき初めて自分の人生に”危機感”をもって立ち向かった。
その時期、私の人生に大きなヒントをくれたのはやはり本だったが、その他にもカウンセリングや占い、自分探しの旅など、出来ることは何でも試したお陰様で自分なりの目標に辿り着き、そこへひたすら走り続けることで迷いは消え、仕事に邁進し、気がついたら今の旦那と出会っていた。
そこから数年の月日が流れ、今年になってアレヨアレヨと以前志していた仕事に返り咲き、おこがましくもフリーで好きな仕事が出来る状態になったというのに、またまたあの頃と似た感情に襲われるのは何故なんだろう?
こんな自分はもの凄くワガママじゃないか?とか、てか人生50年位で終わるんじゃないかとか、意味の分からない負のスパイラルに陥って行く寸前に、答えは突然授けられた。
それは私の日記に何度か登場してくる、私的パワースポットカフェ「Book Cafe Bookish」の明日香さんに選んで頂いた本を読んだことと、昨日実に10年ぶりに訪ねたとあるシャーマン(ユタ)に告げられた言葉が10年前と驚くほど一致していたからだった。
様々な言葉が、ここ数ヶ月の自分自身の状態を明らかにし、どうも曇りがかっていた空から太陽が顔を出し、淀みなく快晴になっていくような感覚があり
「これで良いのだ。」
とバカボンのパパ並みに納得してしまった。
元々、年齢を重ねることに恐怖感はない。
ただ、漠然と人生を過ごし過ぎ去った後で後悔するのが、私の最も嫌悪する生き方なので少しでも早く手を打とうとつい気ばかりが急いてしまう妙な性格なのだ。我ながら面倒くさい。
それにしてもオモシロイことに、自分を納得させる”Key”に出会えた瞬間に、くすぶっていた仮案件の仕事が決まったりプライベートでの短期スパンでの目標が定まるのは、やはり時々見えざる存在が私をガイドしているような気がしてならない。
答えが決まっているなら、なんで遠回りさせるんだろうと恨めしく感じることもあるけど、謎が解けた時の爽快感を思い返すとその遠回りは自分にとって”贈り物”だったんだと気付く。
未来は明るい。
□不惑
子曰、吾十有五而志乎学、三十而立、四十而不惑、五十而知天命、六十而耳順、七十而従心所欲不踰矩。
[書き下し文]子曰く、吾(われ)十有五にして学に志す。三十にして立つ。四十にして惑わず。五十にして天命を知る。六十にして耳順う(したがう)。七十にして心の欲する所に従えども矩(のり)を踰えず(こえず) 。
[口語訳]先生(孔子)がこうおっしゃった。『私は十五歳で学問に志し、三十歳で独立し、四十歳で迷いがなくなり、五十歳で天から与えられた使命を知り、六十歳で人の意見を素直に聞けるようになり、七十歳で自分の心の欲するままに行動しても人の道を踏み外すことがなくなった(行き過ぎた振る舞いがなくなった)』
[解説]「論語」の中でも非常に有名な篇であり、15歳で若くして学問に専心する決意をした孔子の志学の精神、耳学問や書物からの学鑽によって30歳で一人立ちしたこと、それ以降の人徳を積み重ねる人生を簡潔かつ的確に回顧して表現している。孔子は経済的に貧困な貴族階級に生まれたので、正式な学問体系に則って学問を積み重ねたわけではないが、理想とする周(西周)の王道と礼制を政治に復古させるために周の政治体制と礼楽の精髄を学んだ。
古代中国の封建社会では20歳で成人として認められ、30歳で妻帯して社会的に自立するのが普通であったが、孔子もその社会慣習に拠って30歳で立ったと考えられる。40歳で惑わないという事については、孔子の波乱の人生と故国・魯の政治状況を省みると、魯の正統な君主である昭公への忠誠と忠誠を貫くために帰国することを迷わないと解釈することも出来る。孔子が理想としたのは、飽くまで、歴史的な正統性をもつ有徳の君主による政治(王道)であり、実力主義の権力闘争を勝ち抜いた貴族諸侯による政治(貴族)ではなかった。
当時、魯国の君主である昭公は、有力貴族である三桓氏(孟孫・叔孫・季孫の有力な家臣)に圧倒されて国を追われていたが、孔子は三桓氏による魯の統治の正統性を認めることはなかった。孔子が50歳になって知った天命とは、自分に与えられた寿命・才徳・機会では、自分が目指した「魯国の王道の再建」は不可能であるという宿命のことであると言われる。この篇は、私達が人生を如何に生きるべきかという「一般論としての人生の指標」として読むこともできるが、孔子の実際の人生を踏まえて読むと「孔子の実体験から生まれた比類なき道標」として解釈することもできる。
Posted by umiunagi at 03:11│Comments(0)
│日々


















